
こちらの記事では、少人数で運営する弁護士事務所が電話代行サービスを導入し、日々の業務効率化・働き方の柔軟化・対応品質の均一化をどのように実現したかを、ロードマップ形式でご紹介します。
起案や期日管理、面談対応といった高度な集中を要する業務と、代表番号に集まる新規相談・裁判所連絡・日程変更といった入電が同時多発する――そんな小規模事務所ならではの現実を前提に、再現性のある運用モデルを提示します。
・誰かが必ず電話番
・営業電話で集中が途切れる
・長時間の電話相談で予定が崩れる
といった悩みを、一次受付・トリアージ・通知設計でどう解消したのかがポイントです。
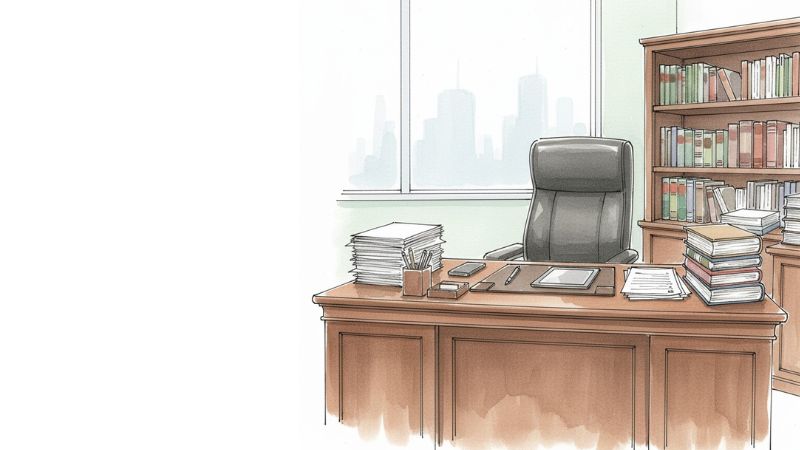
・代表番号の一次受付を代替し、重要コールを可視化
新規相談・面談予約・費用/取扱分野の案内・緊急連絡を電話代行が一次受付。内容と緊急度でトリアージし、担当へ即時通知。
・変更/調整連絡の一元管理でスケジュール最適化
ヒアリング項目(案件種別・希望日時・締切/期日など)をテンプレ化し、チャットに集約。優先度の高い案件だけに集中。
・営業電話のフィルタリング
折り返し対象外の基準を事前に定義。不要な営業対応を削減し、起案・面談・法廷準備に専念できる環境を確保。
「執務は進めたいのに、電話には出ざるを得ない」ジレンマ
弁護士・事務局とも、起案や証拠精査、期日対応には長時間の深い集中が不可欠です。
しかし現実には、面談・法廷・打合せの時間帯に限っても着信は容赦なく発生し、応答できないケースが常態化します。結果、代表番号の着信は留守電や履歴への依存となり、終業後に一斉折り返しで対応する運用が固定化していました。
折り返してみれば、営業・勧誘や定型的な質問(費用、取扱分野、アクセス、必要書類)が想定以上の比率を占め、本来業務(書面の精度向上、依頼者フォロー、期日準備)に割くべき時間を侵食していきます。
さらに、着信の内容と優先度がリアルタイムで可視化されていないため、裁判所や期限の迫る案件と一般的な問い合わせが混在し、どれから対応すべきかの判断コストが発生。
メモの取り方や共有方法も人によってばらつきがあり、情報が属人化して伝言ミスや重複対応が起きやすい状況でした。テレワークや外出が増える中で「電話のためだけに誰かがオフィス待機する」場面も生じ、負担の偏りや不公平感がストレス源となります。
このような断続的な中断とコンテキストスイッチの繰り返しは、起案品質の低下リスクや対応遅延につながり、依頼者満足にも悪影響を及ぼしかねません。
やがて「電話に振り回される日常」が固定化し、業務効率の低下に加えて、常時緊張を強いられることによる精神的負担の増大が積み重なっていきました。
要件定義とスクリプト設計
電話代行を “ただの取次” で終わらせず、守秘義務を前提にした業務インフラとして機能させるため、導入前に【何を外部で一次受付するか/何を事務所へ即時エスカレーションするか】を明確にし、通知フォーマットと話法(スクリプト)を標準化します。
ここでの精度が、その後の運用品質とKPI(中断時間、折り返し時間、一次完結比率)を大きく左右します。
要件(スコープの線引き)
(1)新規相談/面談予約の仮押さえ
希望日時・相談分野・所要時間目安・来所/オンラインの別を取得。重複予約防止ルール(同一案件の連続仮押さえ不可等)も定義。
(2)費用・対応分野・持参書類の定型回答
料金レンジ/着手金・成功報酬の概念、対応領域、初回相談で必要な資料(身分証・契約書・通知書・スクショ等)をテンプレで即答。個別の法的評価や勝敗見通しは回答しない境界線を明記。
(3)裁判所/期限案件/緊急連絡の一次受付
期日・期限・事件番号・相手方名・連絡期限を必須項目化。緊急度タグ(緊急/至急/通常/情報のみ)を付けて即時通知。
(4)営業電話の遮断
商材カテゴリのブラックリスト化(人材・広告・不動産・投資等)。折り返し不要の明確化と、礼節ある断り文言を標準装備。
通知先(チャット通知の標準フォーマット)
必須フィールド:要件/氏名・連絡先/案件種別/希望日時/折返し可否/緊急度/関連期限(期日・提出締切)
任意フィールド:来所/オンライン希望、相手方の有無、紹介元、可連絡時間帯、守秘配慮(折返し名乗り方)
ルーティング:案件別チャンネル(民事・家事・刑事・企業法務等)/担当者別メンション/緊急度でのプッシュ強度を自動切替
SLA目安:緊急=30分以内確認、至急=同営業日、通常=24時間以内。未読監視と二段通知(個人→全体)も設定。
スクリプト(話法・FAQ・禁止事項)
FAQテンプレ:費用目安/対応分野/アクセス/オンライン可否/必要書類/支払方法。文言は誤解を生まない表現に統一(例:「一般的な目安であり、個別案件で確定します」)。
境界線の明示:オペレーターは個別の法律判断・見通し・具体的助言は行わない。初回面談のご案内に留める。
本人確認・秘匿配慮:折返し時の名乗り方(事務所名を出さない等)や第三者リスクへの注意喚起。
コンフリクト予備チェック:相手方氏名・企業名の収集まで(受任可否の最終判断は事務所側)。
NG対応:録音の可否案内、威圧・違法要求へのエスカレーションフロー、長時間相談化の防止(最大◯分で一次切り)。
予約方針(運用ルールの明文化)
受付窓口:当日不可/翌日以降◯時〜、担当指名の可否、相談時間の目安(例:初回30〜45分)、オンライン/来所の基準。
キャパ管理:一日あたりの初回枠上限、連続面談のバッファ時間、期日前の面談優先ルール。
情報取得チェックリスト:相談概要、関係者、期限、希望アウトカム、共有可能資料の有無。
エスカレーション設計(見逃しゼロのための保険)
緊急タグ付与時は即時メンション+電話転送。不達時はバックアップ担当へ自動リレー。
到達確認:既読がつかない場合、5/15分再通知→管理者アラート。
業務時間外:時間外アナウンスでフォーム誘導/緊急専用番号の運用可否を事前合意。
問い合わせ対応の可視化と優先度付け
電話代行の稼働直後から、入電内容がテキストで即時共有されるようになり、「誰が・いつ・何を優先して対応するか」が一目で判断できる体制に切り替わりました。
着信ごとに用件・緊急度・期限が付与され、担当者アサインまでを含めて通知されるため、従来の「履歴を順に折り返す」運用からSLA(対応目安時間)に沿った処理へと移行できます。
・テキストベースの要件整理
面談予約・依頼者連絡・費用質問などを上手く分類し、緊急/期限案件から先に処理するようにしましょう。
裁判所からの連絡や提出期限のある案件には「緊急」「至急」として知らせるなど、事件番号・期日・相手方情報も併記。担当者間の齟齬や取りこぼしが大幅に減少します。
・折り返しの時短
通知には「折り返し希望時間帯」や可連絡チャネル(電話/メール/オンライン)も記録。担当者は移動や合間の時間にバッチ処理でき、コンテキストスイッチを最小化できます。
要件・背景・希望事項が事前に整理されているため、確認から要点伝達までが短尺化し、少ない通話回数・短い通話時間で完結します。
・定型質問の自己完結化
費用目安・対応分野・アクセス・オンライン可否・持参書類などは、FAQテンプレで一次対応が完結。法律判断に踏み込まず案内に徹するガイドラインにより、回答品質が均一化されます。
結果として、弁護士は起案・面談・期日準備といったコア業務に時間を再配分でき、事務局も「本当に手を動かすべき案件」への集中が可能になります。
生産性の回復とストレスの最小化
電話代行の運用が定着すると、効果は一時的な負担軽減にとどまらず、業務品質・働き方・運用の再現性にまで波及しました。
– 中断の激減 → コア業務の品質安定
着信による割り込みがほぼ消え、起案・面談・期日対応にまとまった集中時間を確保。文書の精度や面談の密度が安定し、案件推進のリードタイムも短縮されました。
– 連絡経路の一本化 → 枠再配置が容易に
日程変更や追加要望がチャットに集約され、スレッド単位で履歴が残るため、対応状況が一目瞭然。直近のキャンセル枠を素早く別案件に再配置でき、面談枠の稼働率が向上します。
– 営業電話のフィルタリング → 集中力・速度の向上
折り返し対象外の基準を明確化し、代行側で営業・勧誘を遮断。その結果、事務所が対応するのは「重要な入電」に限定され、判断と折り返しが高速化しました。
– テキスト通知で“見逃しゼロ”
すべての入電が要件・緊急度・期限付きでテキスト化され、担当者に自動ルーティング。既読未読やSLA超過が可視化されるため、対応漏れ・重複対応の発生を抑制できます。
– 働き方の柔軟化と心理的負担の低減
「誰かが電話番」という固定コストが消え、在庁・外出・在宅のどこからでも同じ運用で回せます。負担の偏りや不公平感が解消し、チーム全体のメンタル負荷も軽減しました。
– 運用の学習効果(継続改善)
月次で応答までの時間・一次完結率・誤転送率を振り返り、FAQやスクリプトを更新。改善ループが回ることで、対応品質の均一化と再現性がさらに高まりました。
コア業務の品質を落とすことなく、一次受付とトリアージ、チャット通知の仕組みで着信を整理し、重要案件の初動を加速させることで内見落とし・折り返し遅延といった機会損失を防止できます。
営業電話や定型質問はテンプレで一次完結し、弁護士・事務局は起案・面談・期日準備といった本来業務に集中。その結果、対応のスピードと的確性が両立し、運営に伴うストレスとムダ時間を同時に削減できます。
さらに、通知フォーマットの統一とSLA運用により対応のばらつきが減少し、顧客満足とチームの公平性・再現性も向上します。
ある程度のコール数がある弁護士事務所には、渋谷オフィスの「アドバンスプラン」以上がおすすめです。
アドバンスプランには、以下のような便利な機能が含まれています。
導入時に決めておくべき運用ルール
① 予約/調整のルール化:最短受入・枠上限・オンライン可否・ヒアリング項目(案件種別/緊急度/期限)。
② 変更/キャンセルの基準:前日◯時まで無料・当日キャンセルの扱い・遅刻時の再調整。
③ 営業電話の扱い:折り返し不要の明確化(商材/媒体/営業代行 等)。
④ 案内テンプレ:費用目安・所在地/アクセス・オンライン面談可否・対応分野・必要書類・支払い方法を定型化。
⑤ 通知/担当連携:番号/案件種別ごとの通知振分と担当アサイン、未対応チェックの運用(レポートで可視化)。
「必要な電話だけ自分に届く」仕組みを作ることで、起案・面談・期日対応の質を維持しつつ、問い合わせ対応の効率を高められます。









