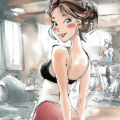こちらの記事では、介護事業者が電話代行サービスを導入することで、日々の業務効率化やスタッフの働き方の柔軟化、さらには利用者・家族への対応品質の均一化をどのように実現したのかを、実際の流れに沿ったロードマップ形式でご紹介します。
介護現場では、
・誰かが必ず電話番をしなければならない
・現場スタッフが電話応対で業務の集中を妨げられる
・施設や棟ごとの情報共有が滞る
といった課題が頻繁に発生します。こうした状況は、サービス品質や職員のモチベーションに少なからず影響を及ぼしてきました。そこで導入されたのが、電話代行サービスとチャットツールの連携です。
一次受付による取次ぎ、通知による情報の即時共有、そして問い合わせ内容の整理と可視化によって、これらの悩みがどのように解消されたのかが本事例の大きなポイントとなります。
・電話受付を代替し、業務中断を防止
利用希望や家族からの問い合わせを代行サービスで一次受付。内容を整理しチャットで即時共有。
・事務所不在時でも連絡が途絶えない体制
電話代行サービスからのSlack通知により、建物間の情報格差を解消。迅速に必要な職員へ共有可能。
・現場スタッフの業務集中を確保
介護スタッフは電話応対の負担から解放され、本来の業務に専念できるようになった。
「事務所を離れられない」プレッシャーと業務中断
事務スタッフは常に「電話を取らなければならない」という意識に縛られ、結果として外出や別の作業に取り組むことが難しい状況に置かれていました。
わずかな離席すら許されないプレッシャーは、日常的なストレスとなり業務効率を低下させます。
さらに、事務員が不在の際には現場の介護スタッフが代わりに電話応対を担うことになり、本来集中すべき利用者へのケアや介助業務が中断されるケースが頻発していました。
こうした環境では、電話応対と介護業務の両立が難しく、対応の遅れや連絡ミスにつながるリスクも高まります。
加えて、施設が複数棟に分かれている場合、情報共有がリアルタイムに行われず、全体としての一体感や組織的な協力体制が損なわれるという悪循環が生じていました。
結果的に、スタッフの精神的負担は増大し、利用者・家族への対応品質にも影響を及ぼす恐れがありました。
要件定義とスクリプト設計
電話代行サービスを導入するにあたり、まず行われたのは要件の明確化とスクリプトの設計でした。
介護事業者にとって電話応対は入居希望や利用予約といった重要な窓口である一方で、緊急連絡や単なる営業電話まで幅広く入り混じるため、効率的かつ確実に整理・処理する仕組みが求められます。
要件としては、
(1)入居・利用予約の仮受付を確実に行うこと、
(2)料金やサービス内容といった頻出質問に対しては事前に準備した定型回答で対応すること、
(3)漏水や事故などの緊急連絡については一次受付として迅速に情報を共有すること、
(4)営業電話や折り返し不要の問い合わせは遮断してスタッフの負担を減らすこと、
の4点が掲げられました。
通知方法については、必要な情報を即座に共有できるようチャットツールを選択。通知内容は「要件・氏名・希望日時・連絡先・折返し可否」といった最低限の項目に統一し、どの職員が見ても一目で状況を把握できるように設計されています。
さらに、スクリプトの整備も行われました。料金体系や住所・アクセス方法、サービス提供範囲、支払方法といった基本情報をテンプレート化することで、対応のばらつきをなくし、誰が対応しても同じ品質を保てるようにしています。
加えて、予約方針(例:「当日不可/翌日以降◯時〜対応可能」など)を事前に明文化することで、電話代行サービス側でも一貫した基準で案内できる体制が整えられました。
問い合わせ対応の見える化と業務効率化
電話代行サービスを導入した直後から、問い合わせ対応の仕組みに大きな改善が見られました。
従来は事務員や現場スタッフが個別に対応していた着信が、チャット通知によって一元的に管理されるようになり、情報が整理された状態で職員全員に共有される体制が整いました。
・チャット通知による一元管理
入居や利用予約、家族からの相談、施設見学の依頼など、多岐にわたる問い合わせが自動的に分類され、優先度の高い案件から処理できるようになりました。
これにより、重要な連絡を見落とすリスクが大幅に低下し、対応のスピードと精度が向上しました。
・事務スタッフの自由度向上
「常に電話のそばにいなければならない」という従来のプレッシャーから解放され、外出や他業務にも安心して取り組めるようになりました。
事務所を離れても通知で状況が把握できるため、スタッフの働き方に柔軟性が生まれ、心理的負担も軽減されました。
・建物間の情報共有改善
複数棟を運営する施設においては、建物ごとに情報が分断されがちでしたが、Slack 通知により全職員が同じ情報を同時に受け取れる環境が実現しました。
これにより、建物間の連携不足が解消され、組織全体での一体感や迅速な対応力が向上しました。
業務効率と職場環境の向上
電話代行サービスの導入から一定期間が経過すると、その効果は一時的な改善にとどまらず、業務の効率化や職場環境の質的向上として定着していきました。
・業務効率の向上
電話対応のストレスや中断が大幅に減少したことで、介護スタッフは本来のケア業務に集中できる体制を確立。
事務スタッフも電話番に縛られることなく柔軟に動けるようになり、事務作業や外部対応の効率が高まりました。結果として、職員全体の時間の使い方に余裕が生まれています。
・職場環境の改善
「電話が鳴るたびに誰かが中断される」という心理的負担がなくなり、スタッフのストレスは大幅に軽減されました。
余裕が生まれた分、同僚同士が互いに助け合える環境が整い、職場の雰囲気も改善。業務の質だけでなく、スタッフの満足度や定着率にも良い影響を与えています。
・組織全体の一体感向上
Slack を通じたリアルタイムの通知・共有により、建物間や部署間の情報格差が解消。全員が同じ情報を同時に把握できるため、判断や対応にズレがなくなり、組織としての一体感が高まりました。
これにより、利用者やその家族への応対品質も均一化され、サービス全体の信頼感が向上しています。
このように、電話代行の導入は単なる「負担軽減」にとどまらず、介護業務の質向上、職員の働きやすさ、そして施設全体のチーム力強化へと波及していきました。
介護サービスの品質を維持するだけでなく、スタッフ一人ひとりの負担を軽減し、働きやすい環境を整えることで、結果的に職場全体の一体感やチームワークも向上させることができます。
電話代行サービスの導入は、利用者や家族にとって安心できる対応体制を確保しながら、職員にとっても無理のない業務遂行を可能にする仕組みづくりにつながります。

1. 要件を明確に切り分けること
介護施設への電話は多岐にわたります。
・入居や利用の予約・見学依頼
・利用者家族からの相談・安否確認
・緊急連絡(事故・体調不良・設備トラブル)
・営業電話や取引先からの案内
電話秘書の目線では、これらを 「折り返し必須」「即時共有」「テンプレ回答」「不要」 のようにあらかじめ区分しておくことが大切です。区分が明確であれば、オペレーターは迷わず正しい対応ができ、現場に必要な情報だけを届けられます。
2. 通知フォーマットの統一
介護現場では「誰が、いつ、どのような要件で連絡してきたか」を正確に伝えることが重要です。電話秘書から見れば、通知が統一されていないと現場で混乱が生じやすくなります。
【氏名】
【連絡先】
【要件】(予約・相談・緊急・その他)
【希望日時/折返し可否】
このフォーマットを決めておくことで、どの職員が通知を見ても即時に判断でき、伝達ミスを防げます。
3. テンプレート回答の整備
よくある質問(例:料金、利用条件、アクセス方法、持ち物、面会ルールなど)については、介護事業者から「FAQテンプレート」を渡してもらうと、電話秘書はスムーズに回答できます。
これにより、現場へのエスカレーションが減り、代行の一次対応だけで解決する割合が増えるため、職員の負担がさらに減ります。
4. 緊急時のルール明文化
介護施設では突発的な連絡が多いのも特徴です。例えば「利用者が急に発熱した」「夜間に設備トラブルが発生した」といったケースです。
電話秘書にとって重要なのは、どこまでヒアリングして、誰に、どの手段で通知するのかが事前にルール化されていること。これにより、連絡の遅れや情報の抜け漏れを防ぎ、緊急対応がスムーズになります。
5. 職場環境への波及効果を意識する
電話秘書から見れば、代行サービスの導入によって現場スタッフが笑顔で働ける環境になり、結果的に入居者や家族からの信頼度も高まります。
「電話番から解放されて介護に専念できる」「情報が全員に同じ形で届く」という効果は、現場のストレス軽減と職員同士の連携強化につながります。
電話秘書自身も「役に立てている」という実感を得やすくなり、サービス品質が安定します。