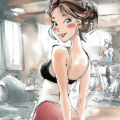こちらの記事では、情報・通信系(SaaS/医療IT領域を含む)を手掛ける中小企業が、どのように電話代行(AI電話含む)を導入し、問い合わせ急増下でも業務効率と顧客満足を両立していったのかを、ロードマップ形式でご紹介します。
特に従業員規模が限られる中小企業では、制度変更やDX推進に伴う問い合わせ急増がボトルネックになりがちです。留守電や当番制では重大連絡を取り逃すリスクがあり、頻繁な着信は社員の心理的負担や業務中断につながります。
本記事では、導入前の課題 → 導入検討 → 導入直後の変化 → 導入後の効果までを時系列で整理しました。
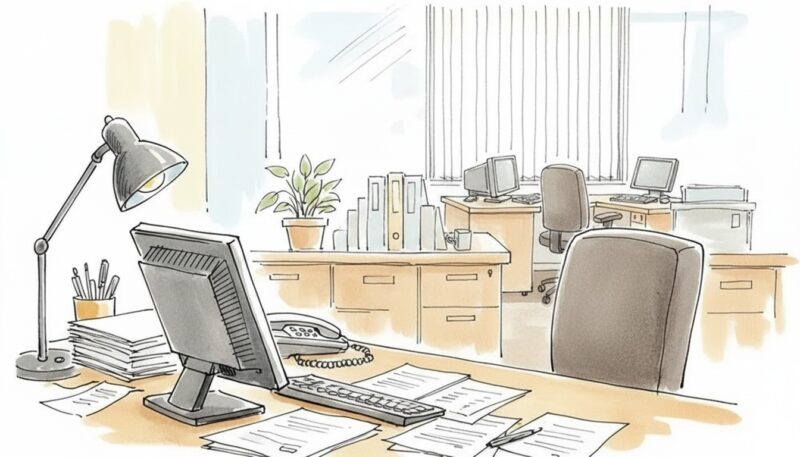
・稼働中の着信を一次受付し、取りこぼしを防止
問合せ種別(見積・技術・契約・障害)を自動分類。必要事項をヒアリングして社内チャネルへ即時通知。
・折り返しの効率化と優先度管理
折り返し希望時間帯の取得、重大度タグ付けで、短時間で要点対応。
・低コスト・簡単運用の仕組み化
管理画面で応答シナリオを自社で変更可能。運用・チューニングの内製化でスピーディに改善。
「問い合わせは増えるのに、電話には出られない」ジレンマ
制度変更や端末要件の見直しに伴い、短期間で問い合わせが急増しました。
新しい規格や運用ルールに関する質問が連日のように寄せられ、社内の代表番号は常に話し中の状態。利用者からは「何度かけてもつながらない」「折り返しが遅い」といった不満の声が増えていきました。
一方で、社員は本来の業務である開発やサポート作業に集中したいものの、電話が鳴るたびに中断を余儀なくされる状況。結果として、メールやチャットでの対応も後手に回り、サービス全体のレスポンス品質にも影響が及びました。
この「電話には出たいが出られない」状況が積み重なることで、社内の負担感やストレスは増大。問い合わせ機会を逃すだけでなく、プロダクト改善や顧客サポートに割けるリソースまでもが圧迫されるという、まさに中小企業ならではのジレンマに直面していました。
要件定義とスクリプト設計
要件:(1)見積・デモ依頼の受付、(2)価格/要件/対応OSの定型回答、(3)障害・緊急連絡の優先ルーティング、(4)営業電話の遮断。
通知先:チャット通知(要件・発信者・組織種別・希望時間・折返し可否・重大度)。
スクリプト:料金・機能・導入フロー・トライアル案内のFAQテンプレを整備。営業時間外は「メッセージ受付+折返し」へ誘導。
採用の決め手:運用コストの低さ/管理画面の操作性が高く、応答シナリオをノーコードで改変できる点。
問い合わせ対応の可視化と優先度付け
・通話録音
通話内容が録音されるようになったことで、重要なクライアントからの電話内容を一字一句確認できるようになりました。
・折り返しの時短
希望時間帯を取得し、短時間スロットで集中的に対応できるように。
・定型質問の自己完結
Q&A対応を上手く活用することで、良くある質問に時間をかけずに応対。社内はコア業務へシフトできるように。
顧客体験の改善と社内ストレスの低減
「何度もかけ直す必要がない」「メッセージを残せば折返しが来る」という安心感が浸透。社内は中断が激減し、重要案件に集中できる運用へ。
テキスト共有によりリモート勤務のメンバーも状況把握が容易になり、情報連携が円滑化。
改善要望:初回着電で緊張する発信者もいるため、より自然な音声・話速・間合いの調整を継続的に改善。
重要度の高い案件を逃さず拾い、社内のムダな中断とストレスを抑えつつ顧客満足を底上げできます。

導入時に決めておくべき運用ルール
① 重要度ルーティング:障害/緊急は高優先で即通知、商談・見積は所定キューへ。
② FAQテンプレ:価格・機能・要件・導入手順・サポート窓口の定型化。
③ 営業電話の扱い:折返し不要の明確化(媒体・代行・ツール営業など)。
④ 通知設計:チャネル(Slack等)とフォーマット(要件/緊急度/希望時間)を統一。
⑤ 継続改善:音声の自然さ・話速・間の調整、スクリプトABテストでCVRを改善。
「必要な電話だけ自分に届く」仕組みを作ることで、顧客体験と社内生産性を同時に高められます。