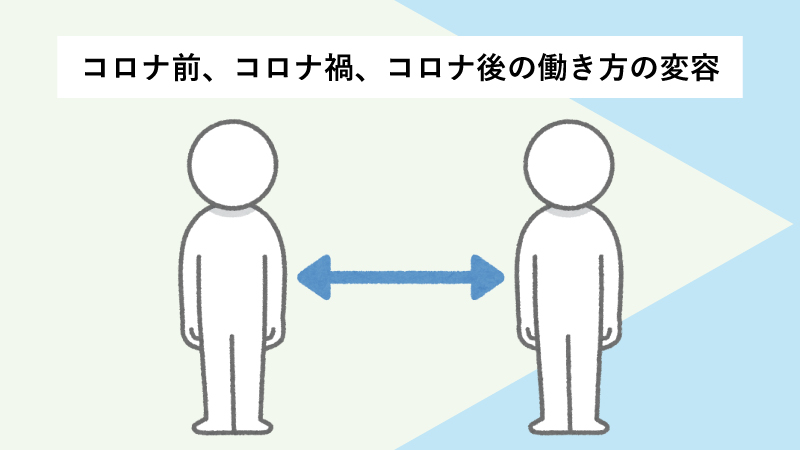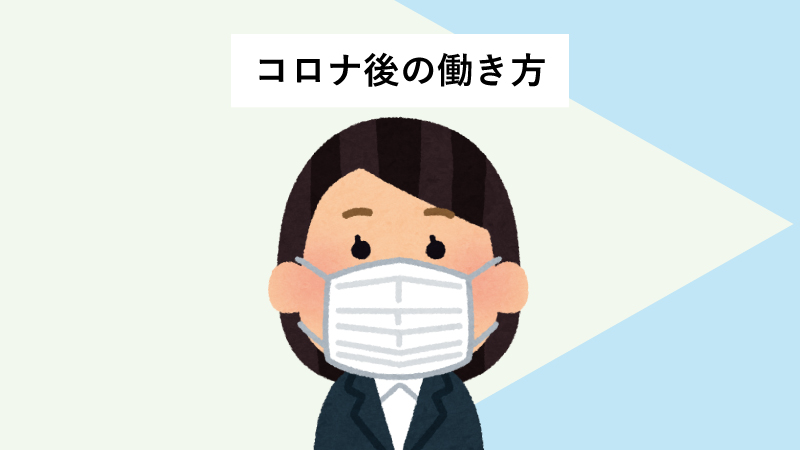出社からリモートワークへ
新型コロナウイルスのパンデミックにより、それまで「会社に出社して働く」のが当たり前だった働き方は急速に変化しました。
緊急事態宣言やロックダウンが発令され、出社や出張が制限される中で、ビジネスの現場は一気に リモートワーク(テレワーク・在宅勤務) へと移行していったのです。
ビジネスに浸透したオンラインツール
これまで対面で行っていた商談や会議、採用面接も、Zoom などのWEB会議システムに置き換えられました。
さらに、社内のコミュニケーションも Slack、LINE、Chatwork といったチャットツールの導入が進み、オフィスに集まらなくても業務を進められる体制が整っていきました。
電話代行サービスの需要増
一方で、社員が在宅勤務となりオフィスを使えなくなると課題になったのが「電話応対」です。
事務所の代表電話を誰も取れない状況を解決するために、多くの企業が 電話代行サービスを導入しました。電話応対をアウトソーシングすることで、出社するスタッフを最小限に抑えつつ、リモートワーク中も会社機能を維持できるようになったのです。
電話応対を担当するのは、経験豊富な 電話秘書のプロ。丁寧な応対によって会社の印象を損なうどころか、むしろ向上させる効果も期待できます。
在宅勤務がもたらした効果
リモートワークにより、社員の中には「通勤時間のストレスがなくなった」「時間の余裕が生まれ生活の質(QOL)が向上した」と感じる人も増えました。特にIT業界などリモートワークと相性の良い業種では、在宅勤務でもこれまで通りの成果を出すことができ、新しい働き方へとシフトする企業も増えています。
新しい働き方を支えるサービス
こうした変化を支えたのが、Zoomやチャットツール、そして電話代行サービス といった便利な仕組みの普及でした。
コロナ禍を経て、企業は「形にとらわれない働き方」を模索し、今なお進化を続けています。
- 目次
- 人にも環境にも優しい、新たな働き方
- コロナ禍で普及した便利なツール・サービス
- コロナ前、コロナ禍、コロナ後の働き方の変容
- コロナ後の働き方
- オフィス再開に伴うハイブリッド型の働き方
- 未来の働き方はどうなる?
人にも環境にも優しい、新たな働き方
総務省もこの「新しい働き方」の流れを積極的に推進しています。同省が示す テレワークの意義・効果 は以下のとおりです。
- ・少子高齢化対策の推進
- ・ワークライフバランスの実現
- ・地域活性化の推進
- ・有能/多様な人材の確保生産性の向上
- ・営業効率の向上・顧客満足度の向上
- ・コスト削減
- ・非常災害時における事業継続(BCP対策)
総務省がまとめる「テレワークの意義・効果」を見ていくと、テレワーク・在宅勤務が様々な観点からも理に適っていることがわかります。
これらを見ても分かる通り、テレワークや在宅勤務は単なる「働き方の一時的な変化」ではありません。社会課題の解決から企業の経営改善、そして社員一人ひとりの生活の質向上まで、多方面にメリットをもたらす理にかなった仕組みといえます。
・少子高齢化対策の推進
少子高齢化対策の推進では、人口構造の急激な変化の中で、個々人の働く意欲に応え、その能力を遺憾なく発揮し活躍できる環境の実現に寄与します。女性・高齢者・障がい者等の就業機会の拡大を目指し、ライフイベントである「出産・育児・介護」と「仕事」の二者選択を迫る状況を緩和します。
更に働き方をの選択肢を増やすことで、これまでオフィス勤務や通勤が事実的に不可能であった人でも働けるように、労働力人口の減少のカバーに寄与します。
・環境負荷軽減
電話バス通勤が減ることで混雑における精神的苦痛・ストレスから解放され、環境面でも交通代替によるCO2の削減等、地球温暖化防止へと繋がります。
・有能/多様な人材の確保生産性の向上
働き方を選べることで、柔軟な働き方が実現され、有能・多様な人材の確保と流出防止に繋がります。また、これまで労働市場に参加できていなかった人材の能力の活用も広がります。
・コスト削減
これまで当たり前のようにかかっていたスペースや紙など、オフィスコストの大幅な削減に繋がります。毎日の通勤が必要なくなるため、通勤・移動時間や交通費の削減等にも繋がります。
コロナ禍で普及した便利なツール・サービス
コロナ禍で在宅勤務や、お家で過ごす時間が増えると共にネット会議ツールの ZOOM、ビジネスマンの間ではチャットツール (Slack、Windows Teams)、電話代行サービスなどが普及しました。
これらのツールやサービスは、コロナ後の「出勤」x「在宅勤務」をミックスさせたハイブリッドな働き方にも必要不可欠です。
コロナ禍で普及した便利なツール・サービスについて >コロナ前、コロナ禍、コロナ後の働き方の変容
コロナ前は、多くの企業で「出社して働くこと」が当たり前でした。
ところがコロナ禍を迎えると、従来の働き方は大きく制限され、企業はそれぞれに対応を迫られました。
・IT企業やネット環境が整っている業種
比較的早い段階でスムーズに在宅勤務へ移行し、リモート環境でも大きな問題なく業務を継続できました。
・大手企業やリモート化が難しい業種
一方で、製造業や接客業などリモートワークが難しい業種では、出社を完全にやめることができず、時間差出勤・出社人数の制限・感染対策の徹底 といった工夫で乗り切る必要がありました。
そしてコロナ後は、企業によって働き方のスタイルが二極化しています。リモートワークの利便性を取り入れつつ、オフィス勤務との ハイブリッド型 を選ぶ会社もあれば、従来通りの「出社中心」に戻す会社もあります。
コロナ後の働き方
この記事を書いている2021年7月5日、イギリスは新規の感染者数が増えるなか (死亡者数は低下)、コロナと共存していく方針を打ち出しました。ジョンソン英首相によると、新型コロナウイルス対策のロックダウンの解除が7月下旬までには行われるようです。コロナ後の働き方はどのようなものになるのでしょうか?
オフィス再開に伴うハイブリッド型の働き方
コロナ後の働き方は「出社」と「在宅」を上手く組み合わせることで、ハイブリッド型の働き方を模索していくことが必要になるでしょう。こちらの記事では、オフィス再開に伴うハイブリッド型の働き方について考察しています。
未来の働き方はどうなる?

Airbnb(ABNB)のCEO、ブライアン・チェスキー氏はインタビューで「これからは出張が旅行に置き換わる」と語っています。
従来、ビジネスマンはわざわざ時間と費用をかけて各地に出張していました。
しかし、いまや Zoom を使えば、世界中どこにいても予定を合わせてすぐにビデオ会議や打ち合わせを行うことができます。
もちろん、リアルな出張が完全になくなるわけではありません。それでも今後は、これまでの出張スタイルに加えて、Zoom のようなWEB会議ツールを並行利用するのが当たり前になるでしょう。
実際に、行政や企業の中には、これまで緊急時に集まって行っていた会議を オンライン会議へ切り替える動き も広がっています。
その影響はすでに数字として表れています。2021年7月の時点で、アメリカでは社員の多くがオフィス勤務に戻らず、出張も大幅に減少。その結果、ビジネスクラスの需要が激減しました。
つまり、多くの企業が「移動して会うよりも、Zoom で済ませた方が便利で効率的だ」と考えるようになったのです。
コロナと共生した働き方を模索
世界に目を向けると、2021年7月現在イギリスはコロナとの共生を目指し始め、いち早くコロナを封じ込めたイスラエルはデルタ株によって再び感染拡大を招きファイザーの3回目の追加接種(ブースター接種)を行なっています。
ワクチン接種が進むアメリカでも、2021年8月現在デルタ株が猛威を振るっており、追撃をかけるように南米ペルーで最初に特定された新たな変異株ラムダ株の脅威にも晒されています。
運行が再開されたクルーズ船では、乗客乗員が2回のワクチン接種を済ませていたにも関わらず20人以上のコロナ陽性者が出るなど、一時は集団免疫獲得か?と思われたアメリカでさえ、再びコロナの脅威に晒されているのが現実です。(しかしワクチンのお陰で死者数と、重篤者数は抑えられています)
このような状況を受けて、米のIT大手フェイスブックでは当社予定していた社員のオフィス復帰を9月から来年 (2022年) 1月に延期することがニュースになりました。
日本はオリンピック以降に大規模な感染拡大を招いており、下手をすると緊急事態宣言を解除できないまま、このまま冬を迎える可能性も出てきていると思います。
このような状況になってしまうと、リモートワーク、テレワーク、在宅勤務で業務を速やかに行えることは必須になり、それに伴うオペレーションや新たにサービスを取り入れることも必要になるでしょう。
今こそ古い価値観を捨て、新しい時代に向けた働き方が求められています。
フィレスター・リサーチによると、私たちはいま新しい20年のビジネスサイクルの入り口に立っていると指摘します。同社はこの時代を「顧客の時代」と呼んでおり、新しい顧客は、好きなときに好きな場所で、製品やサービスの価格を決定し、論評し、購入する力を持っていると言います。